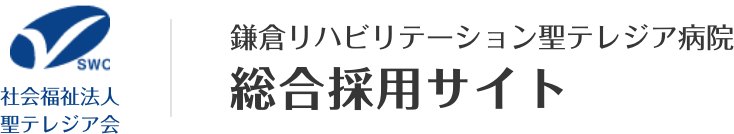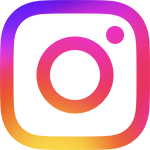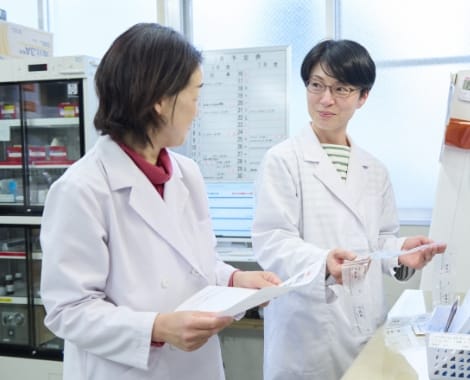働く職場のご紹介
Workplace- トップページ
- 働く職場のご紹介
看護部
回復期リハビリテーション病棟
3病棟全てが回復期リハビリテーション病棟です。
病棟では、患者さんの自立を支援するためにケア10か条に基づいて、日々のケアを行っています。
ケア10か条
- 食事はデイルームに誘導し、経口摂取の取り組みを推進しよう。
- 洗面は洗面所で朝夕、口腔ケアは毎食後実施しよう。
- 排泄はトイレへ誘導し、オムツは極力使用しないようにしよう。
- 入浴は週2回以上、必ず浴槽に入れるようにしよう。
- 日中は普段着で過ごし、更衣は朝夕実施しよう。
- 二次的合併症を予防し、安全対策を徹底し、可能な限り抑制はやめよう。
- 多職種と情報共有を推進しよう。
- リハ技術を習得し看護ケアに生かそう。
- 家族のケアと介護指導を徹底しよう。
- 看護計画を頻回に見直しリハ計画に反映しよう。
さらに、多職種で患者さんの自立に向けた取り組みを行っています。嚥下の取りくみは、嚥下障害のある患者に関しては多職種(言語聴覚士・栄養士・看護師・ケアワーカー)で経口摂取に向けて摂食機能訓練と定期カンファレンスを行っています。
排泄の自立に向けては、院内マイスター制度を取り入れ、排泄ケアのスペシャリストとなるケアワーカーを養成しています。マイスターはオムツの性能や目的に合わせたオムツの選択を学び、漏れない快適なオムツ装着の技術を身に着けます。看護師は排尿障害の患者さんに関して、医師、薬剤師らと共に快適な排泄を目指して活動しています。
認知症の方に関しては、バリデーションを学び、その方にあった個別的なかかわりを行っています。認知症の方もリハビリテーションが進むように、リハセラピストと共に実践しています。また、ケアワーカーを中心に院内デイケアを定期的に行っています。


外来
外来看護師は、神経内科に特化された診療の介助を行っています。
神経難病や認知症患者さん、地域で自分らしく生活できるよう、多職種と連携しながら療養支援しています。

リハビリテーション部
入院リハビリテーション
様々な訓練室でのリハビリテーションはもちろんのこと、「入院そのものがリハビリテーション」という考えのもと病棟での生活を通じた多彩な訓練を提供しています。
また、趣味や仕事を想定した屋外での活動、外出訓練や園芸活動なども実施しています。
他の患者さんやスタッフ同士仲が良く、楽しみながらリハビリテーションに取り組める環境づくりも皆で行なっています。

外来リハビリテーション
外来リハビリテーションの対象は、当院または他院の回復期リハビリテーション病棟を退院した方の他、神経難病等で長期的に関わる症例などもあります。
各症例の疾患特性や社会背景を考慮し、社会復帰を目指し、機能面はもちろん、ADLやAPDL面のアプローチを行います。

訪問リハビリテーション
病気を発症し、病院でリハビリを行って退院された方や、在宅で日常生活活動が難しくなった方のお宅に理学療法士や作業療法士が、週に一度訪問しリハビリを行っています。
主に・・・
- ・身体機能の維持、日常生活活動の介助量の維持・軽減に対する機能練習
- ・自宅の実際の場面での動作練習(トイレ、階段昇降など)
- ・自宅周囲の歩行練習
- ・自主トレーニング、日常生活動作のチェック
- ・ご家族への介助方法の指導
患者さんが地域で円滑に生活ができるよう私たちチームが一丸となってサポートしています!

その他の部署 地域連携事業部
理念
患者さん・ご家族の個人の尊厳を尊重し、患者さんの役割取得や主体性つくりの再獲得に寄与し、地域包括ケアシステム構築の実現を目指します。
運営方針
- 急性期・回復期・生活期をシームレスに一体的支援をおこないます。
- 「医療・福祉・保健の連携による、地域に密着し、開かれた病院としての取り組み」の実現への実践をいたします。
※地域連携事業部は、急性期医療機関と連携し、患者さんまたはご家族の入院前から入院生活までをサポートするための機能を持ち、病棟チームと連動しながら(福祉医療相談室はチームとして)支援を行います。そして、退院後のフォローアップとして地域にある生活期資源との協働を行い、急性期と回復期と生活期を継続的一体的に支援するための連携・連動・協働部門で存在し、鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院の理念・運営方針への実現を実践していくことをアイデンティティとして運営いたします。
地域連携事業部
地域連携事業部は、在宅復帰後のリハビリテーション・ケアの継続的に向けて地域サービス機関と円滑に連携し、患者さんの活動と参加、役割感の取得など、家庭や地域で再びまた輝くために生活・暮らしの質の向上とご家族へのご支援を目的とし、急性期病院と協働し、入院から在宅生活への復帰および復帰後のフォローアップなどをお手伝いする入院・退院支援部門として機能していく部署になります。
組織と機能
地域連携事業部福祉医療相談室は集中し充実したリハビリテーションを行ってもらうため、患者さんのリハビリテーション治療とご家族の生活を阻害する心理的・社会的・経済的要因等や退院後の生活の不安やご心配等に対する相談の窓口として、ご入院の相談から、入外来患者さんのご相談をいたします。
各病棟には専従・専任の医療ソーシャルワーカー(以下MSWという)を配置した体制で支援を行います。
急性期病院、患者さん、ご家族との入院調整・問い合わせの窓口として情報管理室に医事事務員を設置し入院、入院中の受診を含めた調整を行っています。
地域ネットワーク室は、連携先の急性期病院との訪問、カンファレンスへの参加を行い、患者さんが速やかにリハビリテーションに結び付くように機能を果たします。また、地域連携パス会議への参加により、連携、協働への課題や問題を共有し、その解決へ向け、患者さん、ご家族に負担を掛けないような連携に努めます。
組織図
横にスクロールしてご確認ください。

その他の機能
地域連携事業部のもう一つの機能として、一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会(以下病棟協会という)の都道府県別連絡協議会として、神奈川県の協議会運営を行う事務局として活動しております。
誰もがよりよいリハビリテーション医療が受けられることを理念に、リハビリテーションの質的向上を目的に設立された病棟協会との連携を図りながら、神奈川県内での課題、問題を病棟協会に提起し共有していきます。
特に、神奈川県連絡協議会の特徴である、急性期~回復期~生活期との連携・協働の構築を目指した取り組みを軸に、病棟協会へのサポート活動を通し、患者さん、ご家族への支援向上と、地域包括ケアシステム構築へ向け、少しでも寄与できるようにお手伝いをしています。
また、医療福祉協同組合(通称医療協)と連携しながら、社会福祉事業法第2条3項による「無料および低額で診療する事業」の推進をはかり、神奈川県の指導の基、社会福法人立病院としての役目を担っています。
部長からのご挨拶

地域連携事業部 部長
半沢
リハビリテーション=復権、尊厳の回復、主体性の再構築であり、総合リハビリテーションの概念から「その人にとっての支援」に向けた専門技術を考えていくことをモットーに、その人らしい「活動と参加」への実現のための支援を追求しています。
地域連携事業部の持つ強みとして、多様なネットワークを駆使した福祉的視点からの患者さん、ご家族への支援、多職種協働支援の在り方の中ででは、「bio」以外の「psycho」、[social]の観点で評価をする、所謂「生活モデル」の立ち位置を観点とするミクロから、病院同士の病病連携や施設連携、地域にあるフォーマル、インフォーマル資源等との地域連携を軸にするメゾ、そして、全国組織である一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会『10か条宣言』の実践へ寄与していくことの活動を通し、問題提起や共有を図り、マクロへと繋がる働き掛けになる部署として、毎年ごとにテーマを設定、現在のニーズへ向けた取り組みを成していきたいと考えています。